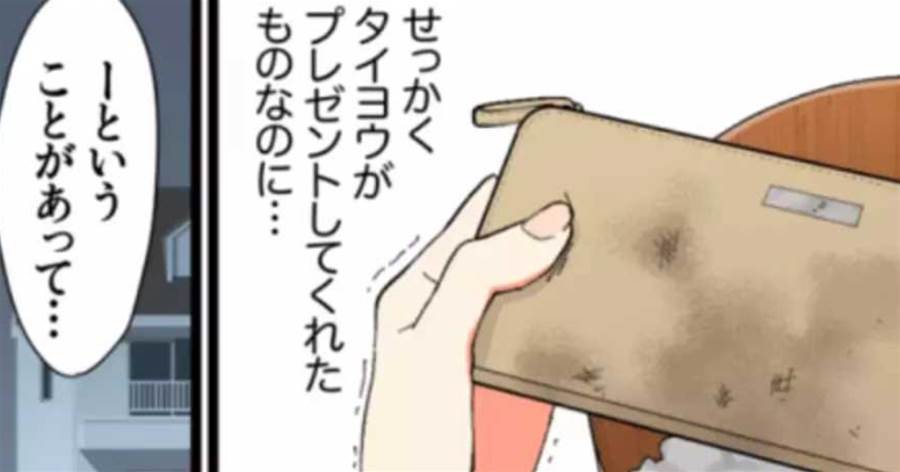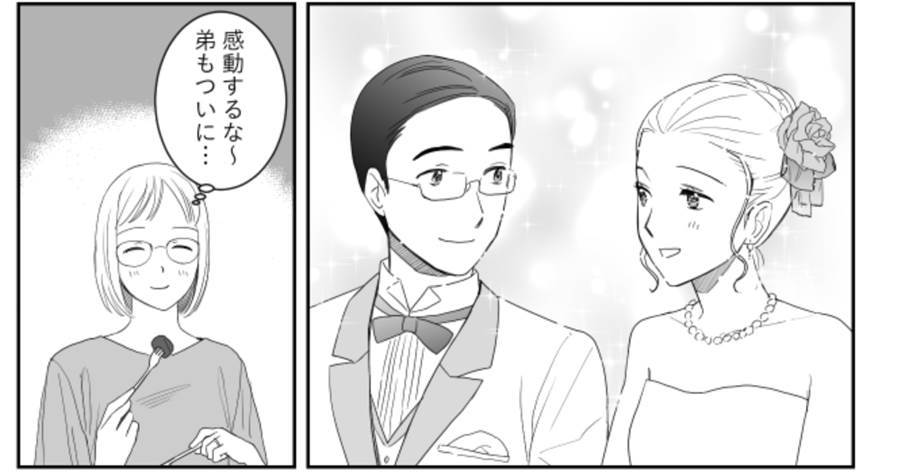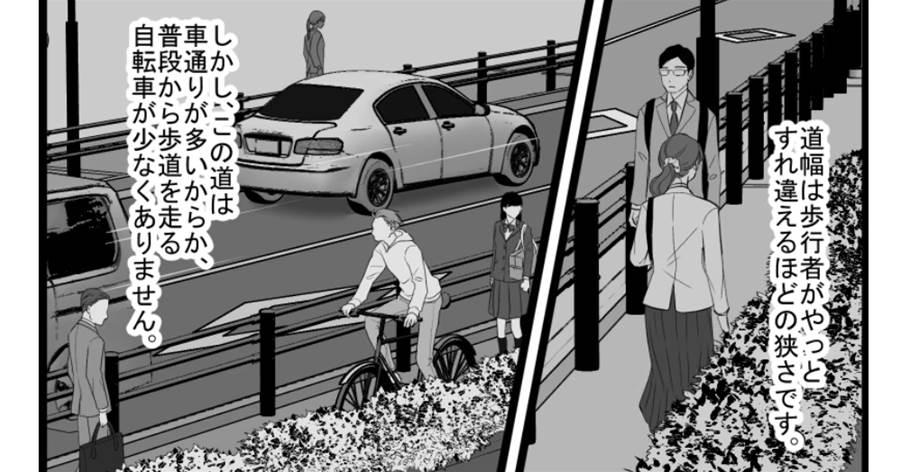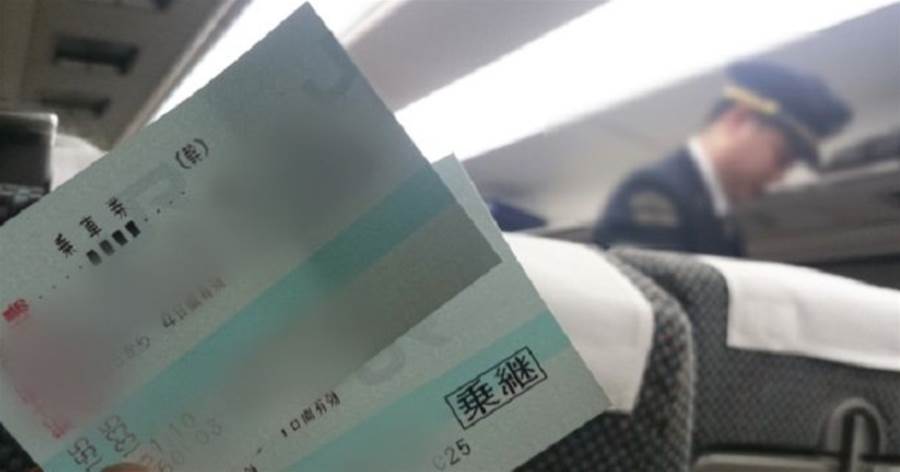江戸時代、犯罪のない理想の社会を目指す一方で、多くの犯罪が存在していました。殺人、傷害、窃盗、詐欺など、現代にも通じる犯罪があり、罪を犯した者には厳しい刑罰が課されました。本記事では、江戸時代の刑罰について、当時の価値観や背景を交えて解説します。
江戸時代中期、全国共通の刑法である「公事方御定書」が誕生しました。それ以前は、罪を犯した者の多くが死刑もしくは追放刑となっていました。犯罪者は社会不適格者とされ、秩序を乱す存在として抹殺または追放されることが一般的でした。
追放刑を受けた者は戸籍から外され、無宿人として生きねばなりませんでした。当時は家を借りるにも仕事に就くにも戸籍や保証人が必要であり、無宿人は再び犯罪に手を染めることが多かったのです。

この状況を憂慮したのが、第八代将軍・徳川吉宗でした。彼は中国の法律を研究し、犯罪の起きない社会の実現を目指していました。吉宗は「公事方御定書」という法典を完成させ、重罪を課すことで治安を維持するのではなく、犯罪者を更生させることを重視しました。
例えば、窃盗罪については、これまで追放刑に処していたものを入れ墨刑に止め、三度罪を犯せば死刑とする方式を取りました。このように、受刑者に再犯を抑止させる恐怖心を植え付け、軽い刑罰で済ませるようにしたのです。
罰金刑と鞭打ち
罰金刑は非常に多く、過料と呼ばれました。例えば、博打を行った者や博打場を提供した者には重い罰金が課されました。また、同じ町内の住民にも連帯責任が問われました。

鞭打ち刑は、窃盗や喧嘩などの軽犯罪に適用されました。受刑者は背中や尻をムチで打たれ、見せしめとしての効果もありました。
追放刑
追放刑は、犯罪者を一定の地域から追放する刑罰です。遠島(島流し)は無期刑であり、将軍の恩赦がなければ戻れませんでした。重追放は、関東・畿内など広範囲にわたる地域からの追放であり、居住地からも追放されました。

死刑
死刑は最も重い刑罰であり、罪の種類によってランクがありました。殺人や強盗殺人などの重罪には即刻死刑が課されました。火刑や磔刑など、非常に残酷な方法が取られました。
江戸時代の刑罰には、現代とは異なる価値観や風習が反映されていました。例えば、主君の命令で家臣を処刑することや、庶民が武士に無礼を働いた際に切り捨て御免が適用されることなどがありました。また、親や上司の仇討ちが奨励され、成功率は低かったものの、家名を守るために行われました。

江戸時代の刑罰は、社会の秩序を維持するために厳しく行われていました。しかし、徳川吉宗の改革により、犯罪者の更生を重視する方向に転換されました。現代と比較しても興味深い点が多く、当時の価値観や社会背景を知ることで、より深く理解することができます。
江戸時代の刑罰に触れることで、現代の刑法の在り方や犯罪抑止の方法について考察する機会にもなります。
記事はまだ終了していません。次のページをクリックしてください
次のページ引用元:https://youtu.be/hDZt7kOpH2Y?si=W7IJ2oVH-6vYaeRJ,記事の削除・修正依頼などのご相談は、下記のメールアドレスまでお気軽にお問い合わせください。[email protected]